
【エンタがビタミン♪】<高見沢俊彦インタビュー>初小説『音叉』執筆「楽しかった」 曲作りにも変化
■何者にもなっていない時代の少年たち
―『音叉』に出てくる「ジュブナイル」という言葉ですが、今回初めて知りました。この作品のテーマのひとつでもあるような気がします。
高見沢:青春期とか、若者を象徴する言葉でもあります。青春群像も含めて、何者にもなっていない時代の少年たちを描いてみたかったんですね。
―THE ALFEEの曲にたびたび出てくるテーマでもありますよね。
高見沢:ああ、そうですね。僕らもキャンパスで出会って、キャンパスで生まれたバンドですから、そこら辺のイメージは強いかもしれない。THE ALFEEの曲では69年とか60年代後半ですけど、これ(音叉)は70年以降、73、74年のリアルに知っている自分たちと同世代のことですね。だからこそ自分ではないんですよ。
■次回作は別の世界で
―今後も執筆は続けますか?
高見沢:表現方法として小説が見つかって、それを一冊に出来たというのは、自分でもすごく大きいですよね。実を言うと、高校時代から密かに小説家に憧れていたときがあったので、夢が還暦過ぎて叶ったというのは、自分の中でも大きくて、こういう物語があったら面白いな、こういう話もいいなと浮かんでは消えていますけど、書き続けていきたいなという意欲は生まれていますね。
―『音叉』の続編の予定はありますか?
高見沢:いや、続編は多分ないと思いますよ。『音叉』はこれで完結していますし、自分の中では『音叉』の世界はこれで終了させて、次の世界に行きたいなと。
■執筆名で漢字を変えたのは?
―ところで、小説を書くにあたり、執筆名としてお名前の漢字を変えたのはなぜですか?(執筆名:高見澤俊彦 「高」は“はしごだか”)
高見沢:別に大きな意味はないんですけどね。普通の「高」と「沢」だと見慣れているかなと思ったので、名前を変えちゃうのもおかしいし、作家をするにあたってそこだけでも変えてみようかなということですね。深い意味はないです。
■小説執筆で歌詞を書くのが新鮮に
―小説を書き終えて、曲作りに変化はありましたか?
高見沢:ソロの新曲『薔薇と月と太陽~The Legend of Versailles』(7月25日リリース)は、小説を書き上げた後に作ったので、歌詞を書くのが新鮮で速かったですね。先に歌詞が、全部ではないですけど一気に出来上がった。(小説の)連載を始めて表現方法が増えたので、今までとは作り方が違ったかな。曲は今までも速かったので、それは変わらないんですが。
―そうしますと、どんどん曲ができますね!
高見沢:そうですね。これならアルバムできますね、THE ALFEEの方も。そこは目指して頑張っていますよ。自分でもここいう曲、ああいう曲…と浮かぶだけでも小説を書いてよかったなと。小説を書いたことが曲作りに関しても絶対にいい方向に向いていると思うんですよ。
―いつも「ソロ活動はTHE ALFEEのため」とおっしゃっていますが、小説はいかがですか?
高見沢:今回の小説は個人的な創作として自分で自分の扉を開けているということなんで、「For THE ALFEE」というより「For myself」という感じがしますね。音楽の場合はチームワークですが、小説の場合は本当にソロ、個人。孤独に書き進めないといけない部分がありますから、逆に自分のペースでラクなところもありますよね。自分が刺激をうけて変わっていくのはTHE ALFEEにとって悪いことではないですから。そこはやって良かったなと思います。
■リフレッシュ方法は必要ない!?
―ところで高見沢さんはどうにも煮詰まったとき、どのようにリフレッシュするのですか?
高見沢:スマホでゲームもやってますし、NetflixやHuluでドラマも見てますけど、小説でいうと新しい分野だったので、書き続けることが自分なりに大変だけど楽しかったですね。筋トレでリフレッシュするぐらいですかね。
―締め切りが大変そうでしたね。
高見沢:曲を作るときももちろんそうなんですけど、作っているときは辛いけど、出来上がったときに自分で「これ、いいな」と思えたりすると、その苦労した分が解消されるので、それ(締め切り)に向かっていますよね。嫌な仕事じゃないから、やりたいことをやっているわけですから、これに勝るものはないでしょ? 締め切りは大変だけど守りたい。だから、納期までに完成したときの喜びは大きいですね。
―すると特別なリフレッシュ方法は必要ないようですね。そういえば、だいぶ前ですが「趣味はTHE ALFEE」とお話しになっていたのを覚えています。
高見沢:今はもう趣味とは呼べない。一種の生きがいでしょうね。その生きがいのためにも、そこはちゃんとやっていきたいと思います。
(TechinsightJapan編集部 関原りあん)

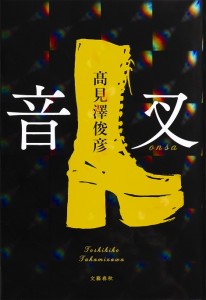






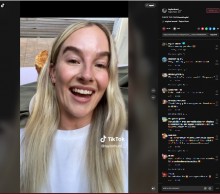


 <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
<