
【エンタがビタミン♪】SNH48・宮澤佐江の姿に本家AKBメンバーも刺激受ける。「格好良い、感動、尊敬」
中国上海でアイドルグループ・SNH48として活動する宮澤佐江に1年間密着した特集が、ニュース番組『NEWS ZERO』で放送された。番組のFacebookには視聴者からも感動したとのコメントが寄せられているが、AKB48グループのメンバーたちも宮澤の頑張る姿に刺激を受けていた。
AKB48の姉妹グループの1つとして中国上海を拠点とするSNH48に、宮澤佐江と鈴木まりやが移籍したのは昨年の11月1日だった。『NEWS ZERO』ではその頃から宮澤佐江にスポットを当てて、密着取材を続けている。さる11月13日の放送では、彼女が移籍してから今年の10月11日にSNH48劇場の公演に出るまでの経緯を特集した。
SNH48のメンバーはダンスがほとんど未経験だったので、宮澤佐江は移籍するともっぱら振付けの指導をしてきた。しかし、その彼女には中国のビザがおりずにSNH48の公演には出られないのだ。今年、1月12日のお披露目公演の前日にあったリハーサル後の反省会で、宮澤が見せた姿は印象的だった。
反省会でみんなが立って輪になっている中、連日のレッスンの疲れからか後ろの方でイスに座って放心状態の者も見受けられた。宮澤はその空気に危機感を持ったようだ。「疲れていると思います。立っているのも辛いと思う。でもせっかく先生が話しているのに、“なんで寄りかかっているの”、“なんで座っているの”。日本と中国は違うかもしれないけど、世界共通だと思う、そういうことは。最低限のことすらできていないよ、悪いけど」と言い放った。
翌日のお披露目公演は振付けもバラバラで合格点とは言えなかった。公演には出られず、客席で見ていた宮澤は「悔しいです。1曲たりとも完璧なところがなかった」と感想を語る。「でもお披露目したからには、やるしかない」と今後の成長を見て欲しいと言わんばかりに表情を引き締めていた。
そんな宮澤自身も、苦手な中国語のレッスンを続けて努力している。SNH48のメンバーたちも、「佐江さんのようなまじめで、厳しい先輩がいるから私たちは恵まれている。彼女がいなければ、私たちはいまだにダメだったかもしれない」とより信頼するようになってきた。
8月30日には、SNH48専用劇場がオープンしてこけら落とし公演が行われた。宮澤はやはりステージに立てなかったが、公演を見た彼女はメンバーとの反省会で「びっくりするくらい、みんなのSNH48というグループが感じられた。いい意味で言うことがない」と嬉しそうに話したのだ。これまでの厳しい指導が報われたのである。
そして10月11日のSNH48劇場公演で、ついに宮澤佐江はメンバーたちとステージに立った。しかも、彼女は中国語であいさつして進行を務め、13曲を中国語で歌ったのだ。メンバーたちとの絆を歌った『支柱』では涙する場面もあった。
宮澤佐江は公演を終えて、観客席に日本から駆けつけた両親を見つけると父親の肩に顔を埋めて泣きじゃくった。気丈にしていても、彼女がどれほど辛い思いをしてここまで頑張ってきたかが分かる光景だ。
特集を見ていたというHKT48の松岡菜摘は、『松岡菜摘 Google+』で「勉強になります。刺激になる」とコメントしている。まだアイドル歴2年の彼女にとって、中国で頑張る先輩の姿はどう映ったのだろうか。
またAKB48の松井咲子は『松井咲子(skc1210) ツイッター』で、「佐江ちゃんもまりやんぬも本当に格好良い、感動、尊敬」とつぶやいた。番組ではほとんど触れられなかったが、“まりやんぬ”こと鈴木まりやも初めてSNH48の公演に出ている。
宮澤佐江は初めてのSNH48のステージを終えて、『宮澤佐江(oyasuminaSAE_m) ツイッター』で「ここまでこれたのはファンの皆さんのおかげ。そして、鈴木まりやがいたからだと思います! 最高の相方だ」とつぶやいている。テレビでは映らなくとも、鈴木まりやも共に頑張っているのだ。
『NEWS ZERO』の村尾信尚キャスターは最後に、SNH48の中国人メンバーが日本を訪れた際に「日本の印象がずいぶん変わった」と話したエピソードを紹介すると、「日中間で政治的な緊張がある今だからこそ、こうした交流がもっと進めば良いのだが」と感想を述べている。宮澤佐江もSNH48の公演を終えて、「言葉は世界共通じゃないけど、パフォーマンスは世界共通だと思う。本当に微力ではあるが、自分が日本と中国の懸け橋になれるならば」と思いを語っていた。
SNH48に移籍した2人は他のAKB48グループとは違った社会情勢での活動が本格的に始まったが、こうなればそれをプラスにしてくれることを期待したい。
(TechinsightJapan編集部 真紀和泉)








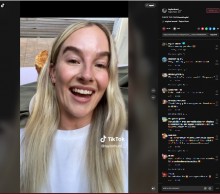
 <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
<